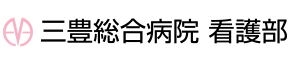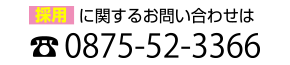わたつみ苑 大宮佳緒里
私が初めて就職した病院に入院していた20代の女性Mさんの話です。Mさんは、その病院で10代の時、看護助手をしていましたが、頸椎の良性腫瘍を発症し、頸髄損傷となっていました。握力低下や知覚鈍麻があり、ADLは何とか自力で食事を摂取できるレベルでした。私が就職して3年目にMさんを受け持つことになり、師長や係長に何年も入院生活を続けているMさんの退院を目標にするように言われました。その頃は、相談員という職種もなく、患者さんが転院や退院をするためには、看護師が医師や理学療法士に相談して自力で行く先を決めなければなりませんでした。私は最初途方にくれましたが、医師に病状を聞き、理学療法士には危険な体位や実際の運動能力、必要な介助の程度を確認した覚えがあります。一番大変だったのは、Mさん本人に意欲が乏しかったことです。退院する希望が持てるよう、カテーテル交換をしながら「この処置は、訪問看護や受診時にできるね」と話し、看護師が毎日行っている援助を自宅でできる方法で提案したり一緒に考えたりしました。また、筆圧が乏しいMさんが、好きな手紙を書けるようにその頃病棟で使い始めたワープロを毎日1時間程度お貸しし、手紙が自分で書けるようになって喜ばれたこともありました。そのような日々を積み重ね、少しずつMさんも自宅でどうすれば生活できるか考えてくれるようになりました。Mさんは母子家庭で祖母と母親、妹の4人家族でした。ご家族には、家族での介護がどの程度可能かということを聞き、その都度話し合いました。お母様は、市役所等に行き、どのようなサービスが受けられるか確認してくださいました。そうして数か月後Mさんは退院していきました。その後私は地元に帰りましたが、年賀状や手紙で「~旅行に行ってきました」「~ができるようになりました」と写真など送ってくれました。
今は相談員という職種があって、訪問サービスなどその人に合ったプランを提案してもらえます。あの時自分は、ただMさんを自己流で退院支援しましたが、はたしてそれで本当に良かったのか、家族の負担は実際どのようなものだったのかなど、その後のフォローができなかったことが心残りです。でも、最近は、この考えを意識して仕事をしている自分に気付くときがあります。その人の望むQOLや生き方、死に方をその都度意識し、それが少しでも患者さんの理想に近づけるよう、いろいろな選択肢や方法を提案していける看護がしたいと考える時、今は貴重な体験をしたと思っています。